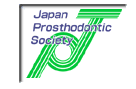
事務局 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9(財)口腔保健協会
TEL 03-3947-8891 FAX 03-3947-8341
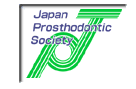 |
Letter for Members 号外(No.1) | |
| 日本補綴歯科学会 | Japan Prosthodontic Society | |
| http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jpds/ | ||
| 発行人 田中久敏 編集 広報委員会 事務局 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9(財)口腔保健協会 TEL 03-3947-8891 FAX 03-3947-8341 |
||
|
||
| 『補綴学会として,一般臨床家が使用できる「咀嚼機能検査法」を1日も早く確立して欲しい.』 | ||
| → 歯科補綴における「検査・診断」の確立は本学会の重点課題です.これまでにも「日常臨床における検査・診断法の検討」と題したシンポジウムを開催しており,そのまとめを学会誌に特集として掲載していく予定です.咀嚼機能検査につきましても早い時期にシンポジウムとして取り上げ,その成果をふまえ,検査法,診断基準に関するガイドラインを早急にまとめたいと考えております. | ||
| 『分科会などをつくって議論を活発にすべきである.学術大会に他分野の講師を多く呼び,会員だけのシンポジウムはやめるべきである.』 | ||
| → 学術大会におけるディスカッションの充実を図るべく,第99回大会から比較的小規模な会場におけるシンポジウム,課題講演,一般口演の開催を行っております.また,シンポジウムの講師も,学際的な活動を行うことを念頭に他分野から広く選定しています.今後とも会員各位からの要望に合致するような課題ならびに講師選定を行います. | ||
| 『学会誌における学術大会の開催日の記載が,金,土曜日の2日のみになっています.企業の診療室に勤務する歯科医ですが,上記の記載では,木曜日の教育研修に参加できません.ぜひ,木,金,土の3日間の記載にして下さい.』 | ||
| → 3日間の開催が必要になってきたことは大変喜ばしいことでありますが,一方では,木、金,土の3日間の学会では、逆に出席し難いとの意見もあります.また,開業や勤務されている先生方からは,日曜日が参加しやすいとの声をよく聞きます.今後,実開催日数を表記することを含めて,実務担当理事会や学術委員会,認定審議会などにおいて検討していくことになろうかと思います. | ||
| 『ポスター発表において,質疑応答の時間を決めていただきたい.発表者がほとんど不在の場合がある』 | ||
| → 十分な学術交流をするためには,当然のことであり,発表者に対し,徹底するようにいたします. | ||
| 『症例報告は,現在のところ,臨床論文として扱われていますが,内容によっては原著にすることを希望します.』 | ||
| → 症例報告はあくまで原著論文ではありません.もちろん,原著論文や症例論文などの区別をあえてしないことは検討の余地があるかもしれません.しかし,むしろ今の世の中は,従来の研究だけの(原著論文だけによる)評価から教育や診療なども含めた幅広い評価へと変わりつつあります.したがって,時代に逆行するような改変は慎みたいという考えも一方にあることもご理解ください. | ||
| 『学術大会や学会誌において「文献的考察」といった項目を設け,研究が日常臨床にもっと直結するようにお願いしたい.「EBM」という概念が臨床医に広まることを望みます.』 | ||
| → 臨床との接点は,本学会の活動方針において最も重視しているところであり,課題講演,シンポジウムにおいて臨床的な課題を今後とも広く採択します.また一般口演,ポスター発表についても症例報告をはじめ臨床報告を広く募集し,臨学の一体化をさらに進めてまいります.文献的考察も当然これらの発表に含まれますので,今後にご期待下さい.また,論文に「JPD」にみられるような「clinical implication」の項目を添付することも検討をしてみたいと思います. | ||
| 『最近はケース報告などもあり,臨床医にも大変興味深くなって参りました.そのPRも含めて臨床医の参加,出席者の増加を期待したい.』 | ||
| → 学会活動を広く知って戴くために,多方面にわたる広報活動を展開していきます. | ||
| 『学会ホームページの情報を常に最新のものにして下さい.また,ニュースレターも有意義であるが,リアルタイムな情報の伝達を考えると,ホームページ上に情報・意見の書き込みのできる電子掲示板の設置が急務である.』 | ||
| → ご指摘の通りです.まずは情報伝達ならびに意見交換の媒体としてのニュースレターを発刊しました.今後は,さらにホームページもこれらの媒体として利用することを考えています.また,広報,編集,学術,認定医などの関連委員会でホームページの管理運営について検討中です.できるだけ早急に管理運営体制を整理し,内容の充実とともに,up to dateな情報をお伝えする予定です. | ||
| 『わかる範囲で次の学会のtopicsなどを知らせてほしい.』 | ||
| → 次の学会のtopicsは学会誌に掲載されますが,歯科医師会誌や歯科関連新聞・定期刊行物・商業誌などへ対しての「学術大会開催案内の掲載依頼」を本大会から行っております.また,ホームページへの掲載も考えております. | ||
|
|
||
|
学会・広報委員会へのご意見・ご要望をお寄せ下さい 広報委員会
|
||
|
||
| 「名古屋グルメガイド」 名古屋といえば「海老フライ(名古屋弁ではエビフリャー)」と思う方がいるかもしれません.確かに名古屋人はエビが好きですが(天むす(千寿が元祖)や海老煎餅ゆかり(坂角)などもエビ入り),それほどではありません.有名な食材としてはナゴヤコーチン(鶏肉)や近海物の魚介類があります.料理では,赤味噌仕立ての味噌煮込みうどん(昭和区壇渓のまことやか中区矢場町の山本屋総本家),赤味噌だれの味噌かつか味噌串カツ(矢場町の矢場とん),そして平たい麺のきしめんが有名です.一方,お櫃に御飯とウナギの蒲焼きが入っていて,1杯目はそのまま,2杯目はネギやワサビなどの薬味と,3杯目はお茶漬けでいただくひつまぶしも隠れた人気です(中区錦のいば昇や熱田神宮近くのあつた蓬莱軒).また,ビールのお供としては,手羽先(チェーン店の風来坊かやまちゃん)や赤味噌のもつ煮込みもおすすめです.夜中にお腹が空いたら,辛い台湾ラーメン(今池の味仙)でもいかがでしょう.ちょっと変わった味を体験したい方は,喫茶店で小倉トーストか,あんかけスパ(中区錦のヨコイ)を注文してみてください. 学会の合間に,関東風でも関西風でもない独自の食文化を育んだ名古屋の味をお楽しみ下さい.ただし,味覚は人それぞれです,お口に合わない場合はご容赦下さい.(文責:名古屋育ちの札幌人 T.I.) |